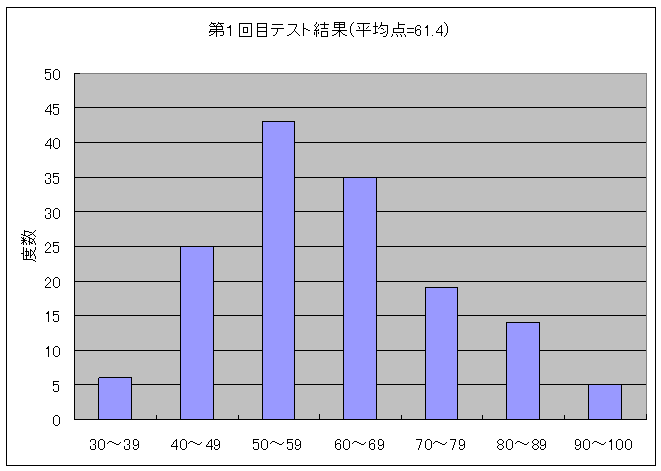
全体的な結果は次の通りです。
平均点=61.4 最高点=100(2名) 最低点=30(1名) 受験生=147名
得点の分布は次の通りです。
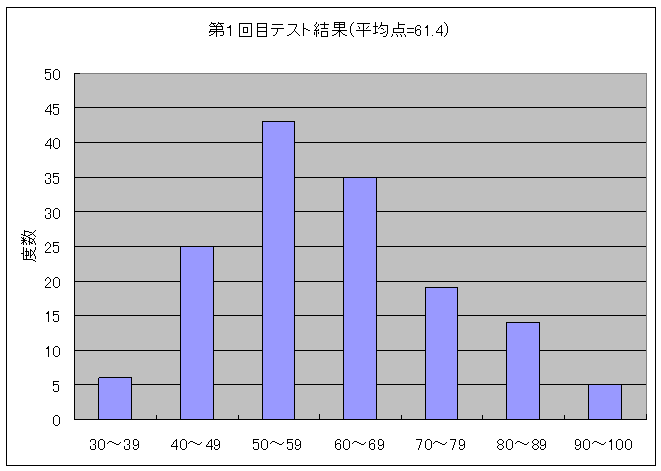
現時点でテストの得点が50点未満の人は31名(21.1%)います。その内応用課題を相当数提出している人がいるので、「成績=テスト得点+応用課題提出数」が50点未満の人は18名です。これらの人は、今後、応用課題の提出および次回のテスト得点の向上によって挽回して下さい。
次に、各問題の正解率は次の通りです。
問題1:73% 問題2:40.1% 問題3:81.3% 問題4:58.9% 問題5:50.9%
回数の決まった繰り返し処理の理解度を問う問題です。平均的には7割の正答率で、健闘しているとは言えるのですが、基本的な内容なので、もう少し正解率を上げたいところです。特に(2)のループ端記号を使った処理の記述方法(⑥)を理解していない人が目につきました。
一般的な終了条件による繰り返し処理の問題です。今回最も正答率が低かった問題ですが、②の”最後に加えた数”の正答率が低かったことが影響しています。選択肢があるのですから、それら個々の場合についてトレースして確かめれば何でもない問題なのですが、多くの人がそれを怠って”勘”だけで答えていたように思います。プログラムは暗記ではなく、”考える”事が重要だと言うことを改めて認識して欲しいと思います。
今回最も正答率が高かった問題です。演習課題で繰り返し最大・最小の問題を採り上げた事が高い正答率につながったものと思われます。
正答率は約6割ですが、誤答の大半は③と④で、その理由は単純でした。と言うのは、誤りの大半は、BufferedReaderクラスのオブジェクト名をAgeFileにしているのに、これを、演習時のプリントで使用したfinにしていた、というものだったからです。もし、このオブジェクト名をプリント通りfinにすると、正答率は軽く8割を越えたでしょう。よく理解せずに単に暗記していた人に警鐘を鳴らすために、あえてオブジェクト名を変えて出題したのですが、予想以上に誤答者が多かったのは残念です。いずれにしても、オブジェクト名は任意ですから、もし、入力ファイルについてはfinと決まっていると誤解していた人がいたらここで、改めて下さい。
これは文を読めば、ほぼ正答できると思って出題したのですが、残念ながら正答率は5割に止まりました。第4章で学習したクラスの意味を理解していた人にとっては何でもない問題だったと思いますが、そこまで準備ができず、テスト時にプリントを見ながら解答した人には恐らく歯が立たなかったのでしょう。実際、この問題はほぼ満点の人と、0点に近い人に得点が二極分化していました。ともかく、クラスは型に、オブジェクトは変数に対応していると考えると、今後の学習も理解しやすくなります。