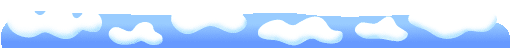この教材は、
Delphiを学習した人が、
C++Builderへ移行を簡単に行うため、プログラミング
Bのテキストです。『
Delphi入門』(2001)をそのまま
C++Builderプログラミング入門用に変えたものであることは、タイトルでもお話しました。そして、本当に基本的な学習の第
8章までを置き換えました。移行への学習は第
8章までで十分理解できると思います。そこで、この
Web教材の(私が希望する)使い方を簡単に説明しておきたいと思います。
 Delphiとの相違点
Delphiとの相違点
やはり、この教材の中で一番重要性であることは
Delphiとの相違点を具体的に理解することだと考えています。本教材の中では、
Delphiとの相違点である個所は下記のように、赤い枠で囲んであります。重視して学習してください。この、相違点をマスターしてしまえば、
C++Builderへの移行は何も問題ありません。
例 2−1コピープログラムを作ろう
 |
また、各ページに
☆『Delphi入門』1-1☆ のように、そのページに対応したDelphi入門の各Webページにつなげました。これは、各自が、Delphiとの相違点や類似点を発見できることをねらいとしています。
 書き直した節
書き直した節
この
Web教材は、『
Delphi入門』(2001)のテキストをそのまま書き換えたと前にお話しましたが、やはりいくら似ていると言っても、言語的には違うので効率よくするためには少し内容を書き換えなければならなかった節があります。下記の節は、内容が変わっていますので、特に重視してください。
第3章 3-6 C++Builderの約束事
第4章 4-4 分岐処理(4)Switch文
その他にも、私が独断で付け加えたりしている点もあります。
各章の学習とねらい
独自のコラム
参考にして下さい。
 アドバイスの挿入
アドバイスの挿入
この教材では、私が
Delphiから
C++Builderへ移行を『
Delphi入門』(2001)のテキストの流れで学習した経験を元にアドバイスとして取り入れています。これは、私が難しいと感じた課題などに付けられています。参考にして下さい。
 課題について
課題について
この教材は『
Delphi入門』(2001)と同じく、
練習問題・
基礎課題・
応用課題があります。練習問題は緑色の枠で基礎課題はオレンジ色の枠、応用課題は黄色の枠で囲んでみました。あくまでも、この
Web教材は自学自習で進めるものなので課題をチェックするということはありませんので、フォルダ作成等は特に求めませんが、同じように学習すると後で見比べるときなどは便利だと思います。
 解答の提示
解答の提示
本教材では、基礎課題・応用課題の1つ1つに解答を付けました。これにおいて、自学自習が進めやすくできると思います。しかし、最初から解答に頼ってしまっては自学自習の意味がなくなってしまいます。あくまでも、課題をやってみてから解答を見るようにして下さい。
以上のことを、念頭におき自学自習をがんばって下さい。